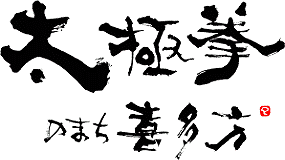2026年度から実施する「太極拳技能検定3段第1次試験」の試験内容について
2026年度より3段検定第1次試験に関する変更事項をここにお知らせします。この変更については、2025年3月1日~3日に開催された2024年度日本連盟講師研修会および、2025年6月21日第29回太極拳技能検定委員会全体会議において確認されたものです。
3段検定都道府県第1次試験として、2008年から「推手基礎套路」を実施してきましたが、実際の太極拳推手の技術を知り、学ぶ機会となるよう、2026年度より「推手対練」動作を用いた試験を実施し、今後の推手技術の発展に役立つように変更したものです。この套路を今後「太極拳四正推手対練動作表」とします。
これらの資料をご参照のうえ、各ブロックおよび各都道府県連盟で実施される3段検定1次試験に向けた講習会等にぜひご参加いただき、受験に備えてください。
[参考] 2026年度第32期太極拳技能検定 3段検定試験
都道府県第1次試験 実施規程
公益社団法人日本武術太極拳連盟
太極拳技能検定委員会
1.実施期間・実施会場:
2026年4月1日(水)から同年8月10日(月)の期間内で、都道府県連盟(以下、実施県連盟と言う)が、任意に指定する期日に、任意に指定する会場で実施する。
2.実施内容:
2008年度より「推手基礎套路」を試験範囲としてきたが、実際の太極拳推手の技術を知り、学ぶ機会となるよう、2026年度より「推手対練」動作を用いた試験を実施する。
1)試験範囲;
日本連盟2025年7月18日付け文発第3954号「太極拳四正推手対練動作表」の演技を審査する。
2)試験方法;
①受験者は下記に定める演武判定審査員とペアになり「太極拳四正推手対練動作表」を演技する。2025年度以前のように推手の相手を指定して受験申請をすることはできない。
②試験は、全体の受験者が10人を超えない場合は、原則として1組ずつ審査を行う。
10人を超える場合は、複数組同時に試験を行うことができる。この場合、何組を同時に実施するかは、会場の広さと審査員の複数組同時進行にたいする判定許容能力に基づいて、実施県連盟が定めたうえで実施する。
③やり直し:試験は、受験者が演技途中に動作の方向や回数を間違えて、演技終了後にやり直しの申請をした場合は、1回に限りやり直しをすることを認める。ただし、2回以上のやり直しは認めない。受験者本人がやり直しを申請しない限り、審査員がやり直しを指示することはできない。
④時間規定:試験範囲の「太極拳四正推手対練動作表」を下記に定める試験進行審査員が読み上げながら進めるため、時間規定は設けない。
⑤審査員は演技終了直後に、都度その場で本人に合否を通告する。
3)合否基準・合否結果の通知方法;
下記に定める演武判定審査員がペアを組んだ受験者の演技を、下記の審査基準に基づいて審査し演技終了直後に合否判定を行う。
4)再試験について;
実施県連盟は、第1次試験を1回のみ実施してもよく、あるいは複数回実施してもよい。
1回目の試験に不合格であった者は、審査終了直後に審査員にたいして1回のやり直しを申請することができる。
やりなおしの試験に不合格であった者は、複数回実施される場合、合格するまで何回でも受験することができる(再試験)。
また、他の実施県連盟で行なわれる第1次試験に申請して、受験することもできる。
3.審査員:
日本連盟太極拳公認A級指導員1人、B級以上の公認指導員1人以上の計2人以上、実施県連盟が指名して実施する。
試験進行審査員;
3段1次試験「太極拳四正推手」対練動作表(別紙参照)を読み上げて試験を進行する。担当審査員は各試験会場につき1名配置。
演武判定審査員;
受験者と甲乙ペアを組み、「太極拳四正推手」対練動作を演武する。演武終了直後、試験進行審査員の合図に従って、ペアを組んだ受験者の「合否判定」をその場で告知する。担当審査員は各試験会場につき1名以上配置。
※都道府県連盟太極拳技能検定委員会にて受験者数に応じた演武判定審査員を配置して実施する。また受験者数多数に及ぶ場合は演武判定審査員の疲労を考慮し、試験途中で試験進行審査員と交替して行う、または交替用の演武判定審査員を配置して交互に受験者とのペアを組んで行う。同様に2組または3組同時に試験を実施する事も可能である。
4.試験委員:
実施県連盟は、審査員の他に、試験会場の管理運営を担当する試験委員数人を、適宜設けることができる。受験者が少数で、審査員が管理運営を兼務することができる場合には、試験委員を設けなくてもよい。
5.実施要領:
実施当日は、下記の要領に基づいて実施する。
─受付;開始式の30分前から受験者の受付を開始する。
─開始式;試験開始30分前に、試験委員は受験者にたいして、試験に関する諸説明・注意と、試験結果の通知方法と通知後の手続き等を説明する。続いて、参加人員を確認し、出場順を発表する。
─試験;審査員はあらかじめ定めた出場順に従って、審査を行う。
─終了式;最後の組の試験が終了した後に終了式を行い、再度通知後の手続き等を説明し終了する。
6.受験資格:
都道府県連盟の加盟団体会員で、前年度まで(2025年度まで)に2段を取得している者に限り、受験することができる。2026年度に3段本試験の受験申請をする予定がない者でも、1次試験を受験し、合否判定を受けることができる。ただし、今年度の第1次試験合格判定は、今年度のみに有効とし、次年度に再び3段本試験を受験する者は、次年度の第1次試験をあらためて受験し、合格判定を得なければならない。前年度の第1次試験の合格判定を、次年度に持ち越して本試験申請をすることはできない。
①受験者は、原則として本人の所属団体が加盟している実施県連盟に受験申請書を提出し、受験する。ただし、本人の所属団体が加盟している実施県連盟の日程が、本人の都合がつかない場合は、近隣の他の実施県連盟に受験申請書を提出して受験することができる。
②不合格判定を受けた場合、他の実施県連盟に受験申請書を提出して、再度受験することができる。
③上記①②いずれの場合も、受験者が所属する都道府県連盟を通して、実施先の都道府県連盟に対して受験申請手続きを行うこととする。受験者本人が独自で行ってはならない。
7.第1次試験の受験申請方法:
本規程に添付する「都道府県第1次試験受験申請書(様式3段1次―1)」に所定の事項を記入し、所属団体長が推薦印を捺印したものを、所属団体を通じて、受験しようとする実施県連盟が設定する申請期日までに、同連盟宛に提出し、同時に、受験料を同連盟が指定する方法で納付する。
8.加盟団体への実施通知義務:
第1次試験を実施しようとする都道府県連盟は、あらかじめ加盟団体にたいして「都道府県第1次試験受験申請書(様式3段1次―1)」を配布しておき、本件の試験期日と会場、受験申請締切期日を、事前に通知しなければならない。この通知は、加盟団体にたいして、原則として遅くとも、締切期日の1~2ヶ月前までに行われなければならないこととする。
9.受験料:
本件の受験料は、受験者1人4千円とする。受験料は、実施県連盟の本件運営費に充当する。
10.受験者の所属する団体への結果通知(実施県連盟→団体):
①実施県連盟は、合否結果を受験者の所属団体に書面で通知する。通知する書面は、所属団体毎に受験者氏名、合否結果を記載したもの(様式無し)でもよく、あるいは、日本連盟宛「合否結果一覧(様式3段1次―3)」を、所属団体毎に分割したものを複写して、該当する所属団体に送付し通知してよい。
11.日本連盟への実施報告(実施県連盟→日連):
実施県連盟は、試験実施後7日以内に、1)「実施報告書(様式3段1次―2)」、2)「合否結果一覧(様式3段1次―3)」、3)合格者の「都道府県第1次試験受験申請書(様式3段1次―1)」のコピー、の3種類の書面を日本連盟に送付して、報告しなければならない。本件の「合否結果一覧」に記載されていない者が、3段本試験の受験申請を行っても受理されない。
12.3段本試験申請時に必要な記載事項(実施県連盟→日連):
「太極拳3段申請・登録用紙(様式3段―1)」の<第1次試験合格確認欄>に、①実施県連盟名、②受験月日、③受験地(都道府県)、が正確に記載されていない申請は受理されない。また、様式3段―1の記載事項と、「実施報告書(様式3段1次―2)」および「合否結果一覧(様式3段1次―3)」に記載されている該当項目および本人氏名が不一致である申請は受理されない。
13.試験範囲=「太極拳四正推手」:
1)動作順序;
別紙日本連盟文発第3954号「太極拳四正推手対練動作表」による
2)動作要領;
1.両足は適切な足幅を保ち、前進・後退・転腰をはっきりと行なう。
2.両手は、柔らかく、軽く保ち、ゆっくりと動かす。両手を、足・腰の動きより速く動かさないこと。
3.体の中正を保ち、目は前方を平視する。体が顕著に前傾したり、ねじれたり、目が下を向くことがないように行う。
4.相手と協調して動く。「沾黏連隨」・「不丟不頂」を保つ。
3)技術課題;
1.定歩「四正推手」を行う際に、放松が保たれていて、ゆったりと均一に動作を行えており、掤・捋・擠・按が概ね正しく行えていること。
2.「四正推手」対練動作時においては掤・捋・擠・按の4種の技法勁法が概ね正しく行えていること。
3.「四正推手」対練動作時で、相手の技法を受けて退く際に、自身の身体の安定を保って安全に受けて退いていること。
※特に推手対練に際しては、怪我や転倒を防止することは必須であり、手腕や上体だけで受けるのではなく、腰胯をゆるめて足裏で受けて、安全に退く技術は必須である。
14.合否判定基準:
下記の場合は、原則として不合格判定とする。
1)四正推手を円滑均一に行っていない場合。
2)対練時の掤・捋・擠・按の4種の技法の内、2つ以上正しく行えていない場合。
3)受けて退く際に4種の技法中で、2つ以上安定して安全に退けていない場合上記以外で、動作が多少、不正確であったり、乱れたり、停頓等があっても不合格判定としない。
15.事前講習会について:
実施県連盟は、第1次試験とは別に、本件試験のための事前講習会を実施することができる。また、第1次試験実施当日の、前半時間帯を利用して、事前講習会を実施することもできる。講習会の実施回数、講師の選定、受講料等はすべて、実施県連盟が独自に定める。受講料は、実施県連盟の運営費に充当する。
16.第1次試験関係書類
①「都道府県第1次試験受験申請書(様式3段1次-1)」
②「実施報告書(様式3段1次-2)」
③「合否結果一覧(様式3段11次-3)」
④「太極拳四正推手対練動作表」
⑤太極拳3段検定第1次試験手続き一覧
以 上
太極拳3段検定 都道府県1次試験
太極拳四正推手対練動作表
2025年6月21日
(1) 試験進行審査員に抱拳礼し、甲:演武判定審査員/乙:受験者、向き合って互いに抱拳礼
(2) 定歩搭手(甲乙右足前・右手上)
(3) 四正手を甲〔掤〕から1回まわす(右搭手までで1回)
(4) 下記対練動作を右搭手から始めて行う
① 甲〔掤〕peng … 乙は甲の〔掤〕を受けて2~3歩退く。
② 乙〔捋〕lü … 甲は乙の〔捋〕に従って退く。
③ 甲〔擠〕ji … 乙は甲の〔擠〕を受けて2~3歩退く。
④ 乙〔下按〕xia an~〔前按〕qian an … 甲は乙の〔下按・前按〕に従い受けて退く。
(5)甲乙交替し甲:受験者/乙:演武判定審査員、(4)同様に対練動作を右搭手から始めて行う
〈 ①甲〔掤〕、 ②乙〔捋〕、 ③甲〔擠〕、 ④乙〔下按〕~〔前按〕 〉
(6)最後に四正手を右搭手で甲〔掤〕から1回まわす(右搭手までで1回)
(7)定歩搭手から並歩となり、甲乙互いに抱拳礼
(8)試験進行審査員に向き直り、抱拳礼して終了